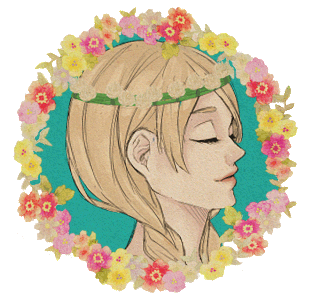| 神様と同じ |
| 火之迦具土ノ命 そう言われれば優しくないかも。 ここに祭られているその神様はもともとイザナギとイザナミの子供として生まれた。 だが、火の神を生んだことで母イザナミは火傷を負って死んでしまうのだ。 それを怒ったイザナギは子供である迦具土を殺してしまう。 神様って案外激しいんだね。 お賽銭を入れ静かに両手を合わせながら3人で頭を下げた。 「・・・・迦具土・・・湧泉音・・・です」 そう,ここの神様と湧泉音の名字は一緒なのだ。最初はその偶然にビックリして一人で興奮したものだった。 「ベルンシュタイン・フォーンリックも名乗っとけよ。でも神さんが混乱するかもしれねえな、ちょっと笑える」 「笑うなんて不謹慎な。神様と同じ名前って、凄いことよ」 「・・・・いや・・・・べつに・・・」 「クールだなお前!もうちょっと他にリアクションないのかよ」 「しっ!静かにして!!」 ああこんなに騒がしかったら神様も呆れてしまうよね。 お願いごとなんてて聞いてくれるわけがない。大丈夫かしら?琥珀のデビューに湧泉音の復学。そして私の未来。 「しっかし、神様ってのは人間の流行先取りだなあ?」 「・・・・・・何・・・・が?・・・・・・・」 立て看板で由来を読み上げながら琥珀が首を振る。 だって、神様とは言え、父親の子殺しだろ? チチオヤノコゴロシ 何て嫌な響きなんだろう。今まで気が付きもしなかったけれど、確かにそう言うことではないか。 ズキンと胸が痛んで思わず息をのんだ。 得体のしれない恐怖感が湧き上がっては渦巻く。 怖い。何故だかしらないけれど怖いのだ。2人は何も気が付いてはいないけれど。 「確か学校で習ったよなあ。黄泉の国にイザナミを迎えに行ったイザナギが振り返ってしまう話」 「・・・・ギリシャ神話・・・も・・・オルフェウス・・・エウリデーケ・・・・」 「吟遊詩人の話か」 「・・・・・琥珀・・・・みたい?・・・」 「オウッ。俺様は魂の吟遊詩人だ。今は亡き恋人の面影を胸に流離うんだよ。ああ、愛しのエウリデーケ」 琥珀ったら。そのおどけた仕草に吹き出しそうになり、さっきまでの恐怖感と不安感は消えて行った。 昔からそうだ。 私も湧泉音もすぐへこむ人間なのだが、琥珀は違う。 逆にそんな微妙な気配を察してか、いつにもまして明るくふる舞い、周りを巻き込んでいく。 自分を憐れんでる時間がもったいない、前を向けよと、言葉ではなく態度で示すのだ。 チャラチャラしたあのポーズの裏には、自分に負けるのが何より嫌いで決して揺らがない芯を持った琥珀がいる。 最もそう思われること自体、彼は好きではないのだろうけど一緒に居て救われたことも多いのは事実だ。 それから私達は一気に階段を駆け下りて、鳥居の近くまでやって来た。辺りには夕闇が迫り私達のバイクのシルエットだけが沈黙している。 |
| みそっかす |
| 「・・・・・おもしろい・・・人・・・」 「おもしろいの一言じゃ、くくれないよサッチン先輩は 」 「すっげえ、パワフルだな。ダンナ、存在感薄いじゃん」 「我が社のナンバー2を捕まえて失礼な。草加さんはああ見えて現場ではすっごい人なんだから」 「・・・・・いい・・・夫婦・・・だよ・・・」 「へえ。珍しいじゃん。ユネがそんな風に言うなんて。こりゃかなりシッカに毒されてるな」 「何?その毒されるってのは?草加さんもサッチン先輩も文句なくいい人に決まってんじゃん」 「わかってるよ。奥さんはともかく草加さんは俺も一緒に現場に入ってるからさ」 「奥さんはともかくってのもムカつく!!」 「・・・・・真っ直ぐ・・・だから・・・」 「真っ直ぐって何が?」 「・・・・うん・・・真っ直ぐ・・・目を見て・・・怖いくらい・・・・ああこの人・・・本当に・・・真っ直ぐ・・だって・・・・・・・・稀有・・・・」 そう言って湧泉音は黙り込んだ。 必死に言葉を探しているようにも見える。 サッチン先輩のあの射るような眼差しの中に、湧泉音は一体何を見たんだろう。 稀有・・・・稀有な人と言いたかったんだろうか。 真っ直ぐに生きる、稀有な人。 傷ついても、苦しんでも、自分を信じて進む人。舞台美術に取り組んでいる時のサッチン先輩は、正にそんな感じだ。自分や周りに決して妥協を許さない。 それが職人と言うものですよ。天花、君の回りはそういう人ばかりでしょう? パパは本当に自分の会社とそのスタッフ達に誇りを持っている。 この地方都市においても、東京に引けを取らない集団だと、前の会社の同僚から電話がかかるたびに自慢する。 みそっかすの私としては少々焦ってしまうのだ。皆の足を引っ張らずにこなすだけで精一杯だから。 ああまた落ち込んでしまいそうだ。 ちょっとブルーな気分を引きずったまま、私達は夕暮れ迫る秋葉神社にやって来た。 日暮しが1日の終わりを告げる一番好きな時間帯だ。 いつも思うけど、神社って何でこんなに背筋がピンと伸びるんだろう。本来は願い事をしに来る場所なのに。まるで罪の告白をするみたいな。 どんなにごまかしても、悪いことは全部見られてる感じの緊張感。今日みたいに自分に自信が無いことを考えさせられる日は特にだ。 まっさらな気持ちで神様に会いに来るって難しい。 「・・・・火伏・・・の・・・神・・・」 「ヒブセ?ああ火を防いで消すってことか?ふうん、じゃあここら辺は神様に守られてるから、火災が少ないってか?」 「ううん。私が生まれる前にこの近所で大きな火事があってママの幼馴染が死んだって聞いたよ」 「・・・・神は・・・・役立たず・・・・」 「バッカ!お前、仮にも神社の境内だろ!神様に聞こえたらどうすんだよ」 「あら、琥珀ったら。神様なんて信じないんじゃなかったの?」 「うっせ!俺は宗教が嫌いなだけなの。だから、有神論者ではある。が、無宗教ってこと」 「何か、言ってることカッコイイね」 「神は、いていいんじゃないか?そう思った方が人間救われるっつうかさあ」 「・・・・神は・・・・救い?・・・・」 「まあ、神さんてのは優しくはなさそう・・・だけどな」 |
| サッチン先輩 |
| 中にはベテラン社員の草加さんと、奥さんでうちの元社員であるサッチンこと咲也先輩がいた。 「サッチン先輩。お久しぶりです」 「ああ、天ちゃん。元気そうね。あの子達が噂の従兄弟さん?」 サッチン先輩は、琥珀と湧泉音に笑顔を向けた。2人はちょっと緊張気味に首をすくめる。 初対面だろうと何だろうとサッチン先輩は遠慮がない。でも決して悪気はないのだ。 思ったことをそのままズバズバ口にする人なので、私も最初は苦手だったけれど・・・・・ けれど、言うだけじゃなく、実際に行動に移す彼女を見ているうちにそのパワフルな生命力に圧倒され、尊敬するようになった。 今では私の数少ない相談相手であり、人生の良き先輩だ。 「ええ?何~やだ、あなた私の後輩になるんだ。」 サッチン先輩がゲラゲラ笑いだす。 「あの美大って変わり者が多いのよ。こんなのとかね!」 そう言って笑いながら自分を指さし、つられて湧泉音も笑っている。 世の中って狭い。 なんと、サッチン先輩と湧泉音は大学の先輩、後輩になるのだ。 サッチン先輩の出身大学なんて、気にしたことがなかった。 私にとって彼女は、会社を辞めても忙しい時はこうやって手伝ってくれるありがたい存在であり、県下ではちょっと名の知れた舞台美術家でもある。 そんなサッチン先輩と親しくなるのに3ケ月はかかった。 それなのに、同じ大学出身と言うだけで初対面の湧泉音と先輩の垣根が、ものの5分位で一気に無くなったのだ。 私と一緒で人見知りする湧泉音にしては珍しい。 きっと彼女の裏表のない気さくさがそうさせるのだろう。 「いやあ、天ちゃんと言い2人も後輩が出来るなんて」 サッチン先輩、出来の悪い後輩でごめんなさい。 今度、先輩がやってるカフェに2人を連れていきますね。 面倒見のいい先輩にかかったら、湧泉音も琥珀もきっと今の自分に対する答えが見つかるかもしれないし。 「ああ来て来て。今うちにも困った居候がいるのよ。例の姪っ子なんだけどね」 昔から、その姪御さんと私は似たところがあると言われていたっけ。でも今は湧泉音や琥珀のことを言ってるみたい。 あっちにもこっちにも困った居候の群れ。 迷える青春ってやつだろうか? 大学を休学中のその姪御さんは、7月の頭から一足早い夏休みと称してやって来たらしいのだが。 姪っ子だからって、容赦しないのがサッチン先輩なんだよね。 「もうさあ。姉貴が手とり足とりするもんだから、大学生にもなって何一つ自分じゃ出来なくてさあ」 「じゃあ、今、姪御さんは何してるんですか?」 「家の前にあるお地蔵さんの世話と野良のボス猫、lagyu(ラグゥ)って言うんだけれど・・・その世話かな?あとまかない」 いかんせん、ボス猫の方がよっぽど人間が出来てるわよ。 そんなちょっと意味不明な言葉を残して、先輩は御主人の草加さんと帰って行った。 猫より劣る人間性って・・・・・? |
| 忘却の河 |
| 人は生まれ変わる時、死の谷を歩き忘却の河の水を飲む。そこで初めて前世での記憶がリセットされ、次に生まれ変わる人生を自ら選ぶそうだ。 最も,湧泉音にしても実際に見たわけではないので本の受け売りなんだけれど、でも人間がそうなら動物も同じではないかと言う。 「日本の三途の川と同じだな。」 「・・・・河は・・レーテー・・・・・渡し守も・・・いる・・・」 「渡し守?ますます三途の川みたい。」 「・・・・カロン・・・って名前・・・」 「オイ!カロンって、俺のバイクの名前はそこから来たのかよ。渡し守かよ!お前のは確かハデスだよな」 「・・・・冥界・・・王・・・」 「はあ~?俺のは渡し守でお前は王かよ!逆じゃね?普通」 「いいじゃない。私のだって冥府の番人の名前だよ」 「シッカのはなんつったっけ?ヘ・・・へ、何とかだよな」 「ヘカテ!!」 「ああ!そうそう。お前が中学の時・・・・」 「いいの!そんな昔のこと言わなくて!!」 「・・・・好き・・・だよね?・・・みんなこういう・・・の」 「私のはママのキーホルダーから取っただけだよ。さあお二人さん今日はもうこれで仕事は終わり。秋葉神社に行くよ」 「えっ?今からかよ!」 「・・・・実家・・・行くんだ・・・」 「ハイハイ。そう言うこと!」 うちの会社の経理部門は実家の方にある。倉庫の番人兼居候の身としては、一応家賃と言うものを払わなければならない。 溜まった業務日誌を持って行くついでもある。 この前は死んだ子猫のことで動揺して行かなかったので、今日は何としてでも2人を連れてお参りに行かなければ、またしばらく行きそびれてしまうに違いない 。 神社だって縁がなければ、なかなか参れないものなのだ。 「で?本名の久慈院琥珀がいいの?えっと、こっちの、長いな、ええっと琥珀・ディートリッヒ・フォーンリック?ああ、ご両親が国際結婚だからねえ。どっちも本名になるんだ。やっぱりそうなると、K・O・H・A・K・U かなあ?ビジュアル系で売り出すならね」 目の前の石村と名乗るプロデューサーのオヤジは1人でしやべり続ける。 琥珀はいつもの癖で、無意識に膝を揺すっていた。こんな時、隣にシッカが居たら思い切り膝を叩かれるか、あの大きな瞳で睨まれるかなのだが、相変わらずオヤジの話は続く。 「ウゲエ~」 石村が去った後、琥珀は顔をしかめてうぜえと言いかけ、後ろに人の気配を感じ慌てて言葉を濁した。 振り向くと、彼をここに誘った雨池ディレクターが微笑んでいる。 「雨池さん。いつこっちに戻ったんすか?」 札幌出身の雨池ディレクターは、こちらにある本社と札幌にある支社を行き来している。 本人曰く、あまり都会が好きではないのと夏の暑さが耐えられないのとで、もっぱら支社に居る事が多い。 「久慈院君、元気そうだね。石村さんに捕まってたからいつどのタイミングで話しかけようかと思ったよ」 「はあ、芸名をどうしようかって言われて、別に俺、そんなことどうでもいいし。ビジュアル系って何すか?俺は曲で勝負したいんすよね」 「ううん。困ったね。石村さんはやり手だから、任せておけば大丈夫だと思ってたんだけどね。どうやら君を売り出す路線が、君の考えとは違うらしい」 「俺、アイドル目指してるわけじゃないっすもん」 「まあ、大人の事情ってやつだね。いきなり持ち歌で勝負するより、いわゆるアイドル路線で売り出しておいて、実は作曲も出来ますって言う意外性。石村さんはそこを狙ってるんじゃないかな?」 「意外性も何も俺は俺っすから。ただ自分の作った曲を歌うだけで何が悪いんっすか?」 困ったね、と雨池ディレクターは呟き、琥珀の肩に手を置いて軽く叩きながら去って行く。 ボンヤリと琥珀はそんな雨池の後姿を思い出していた。 天花お薦めの稲荷神社に参った所でこの問題が簡単に片付くとは思えない。 「まっ・・・いいか!」 自身に言い聞かせるように、琥珀はドアを開けた。 |
| マロザラシ |
| 「それって、ある意味オカルトだよな」 「情緒のない言い方だね!半分は日本人でしょ?」 私達は波打ち際を歩いた 色とりどりの出店と行きかう多くの人々。 やがて、盆踊りに続いて花火大会が行われ、夜空に夏の終わりを告げる大輪の花々が咲く。 その時だけは、仕事を請け負っている者の特権で物凄く近くから花火を見ることが出来るのだけれど、あまりにも真上の花火と言うものは、首が痛くなるものだと2人に話していた時だった。 「・・・・・何か・・・いる!」 最初に気が付いたのは湧泉音だった。白くて小さくて丸いものが砂の上に横たわっている。 そして、それは微かに動いているのだ。波のせいではない。 「アザラシ??」 慌てて駆け寄った私達は、一斉に声を上げた。 「・・・いや・・・ねこ?」 「猫?本当だ。行き倒れの猫だ」 そっと抱え上げると弱弱しい目が真っ直ぐこちらを見つめている。 「生きてる!はっ!すげっえ!今度は命を拾ったぜ!」 「この前死んだ子猫の生まれ変わりかもね?」 「・・・・・生まれ・・・変わり・・・?」 「あいつらお人好しそうだから、もう一回生まれ変わって会いに行けって、神様がチャンスをくれたのかもな。よしよし、お前運の強い奴だな」 そう言って、2人は再び首にかけてあるタオルで子猫を包んだ。 「・・・・汗・・・くさい・・・ごめん・・・」 「ほれほれ、新しい家に帰ろうな」 目の前の命は今、確かに2人の手の中にあった。 左右の瞳の色が違う、オッドアイ。 しかも、額にはまるで眉毛を掻いた様に黒い毛が生えている。 まろ眉のあざらし猫。 その子はいつしか<まろざらし>と呼ばれ会社の机やパソコンを遊具に、椅子をベッドにして育ち、社員のランチタイムを恐怖に陥れ挙句、カップラーメンが大好物と言う<もよこ>と並ぶ変な生き物になってしまったのだ。 「まろざらしお前、本当に面白い顔してるな。死んだあの子猫とは似ても似つかねえけど、本当に生まれ変わりかよ?」 「・・・・そう・・・・信じ・・・・たい」 「そうよね。その方が何となく救われる気がするもん」 「だとしたら、前世の記憶とか・・・あるのかな?生まれて数か月で車に撥ねられて死んだなんて、そんな痛い記憶、俺なら絶対いらねえな」 「・・・・忘却の・・・河・・・」 「忘却の河??」 |