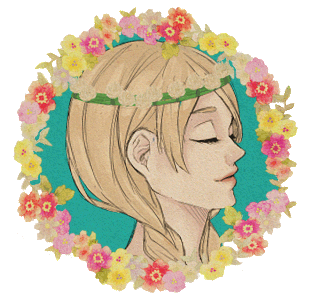| 神の見えざる手 |
| 茅乃へ。 突然こんな手紙を書いてごめんなさい。 結婚 おめでとう。・・・・なんて遅いよね今頃。 実は子供2人を連れて別府に帰ろうと思っています。 恐らく夫とは別れるでしょう。貴女の言った通りになっちゃった。でも仕方がないわね、これが私の人生だから。 実家の母は相変わらずです。父は倒れた時から寝たきりで私のこともあまり解っていません。あれだけ私に酷いことをしたのにね。 何も覚えてないのよ、都合がいいよね。 母のことも許していないけど、結局、私も同じような男を選んでしまったわけだから、似た者同士かもしれません。 だからせめて子供達だけは私が守ってやりたいの。でも私がこんなだから上の子がね、ものすごく私に気を使うの、まだ小さいのに可哀そうよね。 いつかはきちんと話し合うつもりですが、今はとにかく夫から逃げることが先かなって・・・・ しっかりしなくちゃいけないなって思います。 また、結果は報告しますね。 翔子 湧泉音と琥珀に共通する記憶のようなもの。 あの朝、3人で黙り込んで以来、漠然とした何かを追い求めるかのように自然と足は秋葉神社に向かっていた。 3人で訪れるのはこれでもう5回目だ。 「初めてここに来た時、神様はいるって琥珀は言ったよね?」 「ああ、言ったさ。もっともこうやって地上に生きてる俺達が知る術はないけど・・・多分・・」 「・・・・多分・・・・見えない・・・だけ?」 「そうだね。神様の存在を知りたいって思っても、そんなの無理だし・・・でも、人って何か困ったり迷ったりして、答えや助けが欲しい時は祈るじゃない?」 「あ~俺も進級テストの前、初詣で必死に祈ったワ!」 「琥珀ったら・・・祈るだけで何もしない人には神様は振り向いてくれないと思うよ。祈りも大事だけど、やっぱり毎日一生懸命努力して生きることが大切で、そんな人には・・・・・・」 「・・・・・人には・・・・・・?」 「神さんは何らかのサインを送ってくれると思うぜ。まあ、俺の勝手な解釈だけどな」 「ちゃんと解ってるんだ。でも琥珀はミュージシャンを目指していることに迷いはないんでしょう?」 「ん?いや迷うぜ。迷ってばかりだと思う。今のレーベルでいいのか?とかデビュー曲は何がいいのか?とかな。」 「えっ?レコード会社を変えるの?そんなこといまさら・・・」 「変えるかどうかはまだ解んねえって。ただ、自分が音楽の道を目指すことに迷いはない。そこがぶれない限りは大丈夫だと思う」 「・・・・ぶれない・・・・・・」 「琥珀みたいにぶれないでいられるには、どうしたらいいんだろう?今自分がやってることとか、進んでる道が間違ってないって、どうやったら思えるんだろう?」 「逆に、一杯悩むことじゃね?迷うって言うよりこれでいいのかって思う自分とこれっきゃないって、思う自分とのせめぎ合いつうか」 「自信家の琥珀さんからそんな言葉を聞くとはね。傍から見てたら疑いようがないのに、それでも悩むんだ。」 「こう見えて謙虚なのよ、俺様は・・・・まあ、努力して生きてりゃ神の見えざる手ってやつが働くんじゃねえの?」 |
| 翔子 |
| 茅乃へ 辛いことがあると貴女に会いたくなる。 貴女なら何も言わなくても解ってくれるから、私の悪い癖ね。 私は、ずっと自分の名前が嫌いだった。 翔子なんて、一度も飛べなかった人間なのに。 子供の時から翼があればと恋焦がれていたくせに、いつの間にか飛ぶことを忘れてしまった。 いえ、もしかしたら自分で翼をたたんでしまったのか、生まれた時から折れていたのかもしれないけれど。 貴女の名前は植物が好きなお母さんがつけたのよね。 じゃあ将来、貴女が結婚して、ベビーが出来たら同じようにするのかしら? 私もせめて人から愛されるように、子供には花の名前をつけたいと思っていたのですが・・・・・・実は2人目が出来ました。 これで少しは夫も変わってくれるといいなと空しい期待をしています。 でも正直、生むのが怖いです、中絶する勇気もありませんが。 なんだかとりとめもない文になって、何を言いたかったのか? ほとんど愚痴になってしまってごめんなさい。 また、手紙を書きます。 翔子 深い溜息と共に翔子はペンを置いた。 傍らには小さなあどけない寝顔がこちらを向いている。 翔子はそっと毛布を掛けなおすと、わずかに膨らんだ自らのお腹に痣だらけの手を置き、少しためらいがちに部屋の灯りを消した。 その哀しみに満ちた横顔にも、凄まじいまでの殴打の痕が浮かび上がってはいるが、それよりも深い夜の闇が覆い隠していった。 「んんん?ニッケだっけ?ハッカじゃねえのなこれ」 琥珀もいつの間にかこちらに来てからの朝食は、シナモントーストになっている。 「俺はやっぱ、ピーナツバターのクランチタイプだな」 「・・・・うん・・・それ・・・琥珀に・・・教わった」 「まあこれもいけてるよ。シナモンは無かったけど昔、おふくろがグラニュー糖じゃなくって普通の砂糖・・・・・ん?違うなおふくろじゃない・・・自分か?」 そう言いながら琥珀は自分の頭に手をやった。 「これって、既視感だよな。デジャヴってやつ」 「はああ~」 「何だよ。変なこと言ったかよ」 「そうじゃなくって、ゆねも同じこと言ったの。」 「ユネ?が?」 2人は1人黙々と口を動かす湧泉音の言葉を待った。 「・・・・モノクロの・・・・デジャビュ・・・・」 「何でモノクロなんだよ?」 「・・・・色がない・・・・世界・・・・」 「色がないって?モノクロ写真か?」 「・・・・・色が・・・・見えない・・・・」 「見えないって?」 「ちょっと待ってよ。琥珀は?琥珀のはどんな感じなの?ゆねのと違って色がついてるの?」 「俺のは・・・・何か近くて遠いって言うのかぼんやりしてる。ユネのがモノクロなら、俺のはフィルターをかけた写真みたいな感じかなあ」 3人は黙り込んだ。 何なんだろう。湧泉音と琥珀の2人が同じ光景に記憶があると言いだすなんて・・・・・ いや、この場合記憶ではないのかもしれない? |
| 海を目指して |
|
私達3人が揃うと琥珀がいつも1人で喋っては自己完結していく。 それに時折私が反論するのもいつものことで、湧泉音が口をはさむことはあまりない。 転校しそんな2人と居る居心地の良さを捨ててから、一層孤独になりはしたが、自分のことを誰も知らないと言う自由さに何処かホッとしたのも事実だ。 幼稚園から高校の途中まで一貫教育の学校に居た時は、お互いに知っている安心感もあった。しかし、同時に周りがイメージした自分の枠をはみ出ることも出来なかった。 もどかしいと心のどこかで思っていた。 では、どうしたかったのか?と問われても答えは出ない。 だから、湧泉音が空になったミルクのグラスを回しながら、何故ここに居るのか?と言う疑問を私に投げかけた時、かつて自分自身がいた深い心理の海の底に今、湧泉音がいるのかもしれないと思ったのだ。 何のために生まれたのか?と言う自身への問いだ。 「シッカ、あんまり悩むなって!今を生きろよ精一杯」 ぐずぐずと思い悩んでいる私を見かねて琥珀がそんな言葉を私に投げかけてきた時がある。 「お前の人生を誰も代わりに生きていくことは出来ないんだぜ。でも助けることは出来る」 ただ助けに行って、一緒に溺れるわけにはいかないから、まず泳ぐ前にきちんと準備運動しておいてくれよ、とも。 琥珀なりの優しさと人生訓だ。 カナヅチだから、はなから海には入らないと答えた私に、浮き輪でも舟でも使ってとにかく海に入れよ、と言い放った。 「半径1キロ以内の人生で終わるなよ。つまらねえだろ、せっかく生まれて来たってのに!海を目指せ!指切りげんまんな!」 琥珀の言う海とは人生のことだ。 浮き輪や舟は生きていく方法と言うこと。 そんな琥珀とのやり取りは私が無事に高校を卒業するまで続いた。 海を目指す約束を守れたかどうかは解らないけれど、デビューが決まって直ぐに電話をくれたのは、琥珀自身が自分の言った言葉に責任を持とうとしていたのかもしれない。 そのおかげで、海に漕ぎ出す方法を見つけた私は、何とか今のところは遭難も難破もせずにいられる。 但し、たった一人の航海は、物凄く辛くて心がすくむ。 時折くじけそうになる、そんな自分との戦いなのだけれど。 琥珀がしてくれたように、湧泉音に対して私も出来ることがあるだろうか? そんなことを琥珀に聞いたら、自分の舟に乗せてひっくり返るのがオチだと言われるかもしれない。 ゆねはせいぜい泳げて25mだと、笑うだろうか。 湧泉音は相変わらず黙ったまま、杜を見つめている。 「帰ろうぜ。腹減ったよ。ほら」 握りしめていたキーホルダーを琥珀は私に差し出し、少し怒ったような眼差しを向けた。 「お前、これにインスピレーションを得て中学の時、絵を描いてたよな?まだ完成してないのか?」 「うん・・・・まだ。何かが足りない」 「その何かが足りないって言う絵に題名はあるのか?」 「ヘカテの・・・翼」 |
| 悪意 |
| キーホルダーと一緒に入っていた手紙や新聞の切り抜きは、恐らくその亡くなった幼馴染のものなのだ、と気が付いた時には箱ごとどこか別の場所にしまわれていた。 やがてそれすらも忘れかけていた頃、こちらに引っ越して来て倉庫の片隅に置かれているのを見つけたが、そのままにしてある。 ヘカテは元々安産の神様だ。 妊婦のもとに寄り添い、分娩を助ける。 けれどあまりにも強い霊力を持つが為に、それが人間に伝わることを恐れた、他の神々から冥府へと落とされ、死と再生を司る番人となった。 祈りを捧げる者には限りなく優しい、清めと贖罪の神でもある。 「・・・・・力・・・・故・・・・」 「神様とやらの世界も妬みや裏切りが横行したわけか。俺様も気をつけよう。才能の有る奴は足を引っ張られた上に、悪意に晒されるからな」 「ちょっと、そこで何で私を見るのよ」 「見てないって。自意識過剰だよお前、俺はただ単に例えを言っただけだよ。た・と・え」 「そんなことない。絶対、私のこと言ったよ。ねえ、ゆね??」 「・・・・悪意・・・晒される・・・」 「ゆね?どうしたの・・・誰かに苛められたの?」 「・・・・いや・・・・・・」 「俺たちは見てくれからして違うからな。そこからして一般の人間の心の物差しに当てはまらない。で勝手な憶測でものを言われる。髪の毛が長すぎるだの、性格が派手だの、不良に決まってるだの」 「・・・・うん?・・・・」 「要するに、存在自体が知らず知らずのうちに周りに不快感を与えちまうのさ。不快=排除の図式。それが悪意・・・違うか?」 「ゆねはともかく、琥珀の場合はその口の悪さのせいじゃない?もっと優しい言い方すれば誤解されることも無いと思うけど?」 「じゃあシッカは、誤解も偏見も無く居られたか?いつもニコニコしてりゃ攻撃されなかったのか?」 「・・・・・攻撃・・・・」 「見かけは外国人のくせに英語が・・・俺たちの場合はドイツ語だけどな。喋れない変なヤツって言われ続けたじゃないか?幾ら俺たちが普通に振舞おうと努力しても・・・・な」 「そりゃ宇宙人とか随分ひどいこと言われたけど」 「怖いから憎むんだきっと。狭い子供の世界の中では、俺達は未知の人間なんだよ。髪の色や目の色が違うってだけでな。だったらいっそ関わらずにいるか、憎悪の対象にするかだ。」 「確かに、私達って友達少ないよね」 「・・・・・憎まれる・・・悪意・・・」 「そんなんで落ち込むなって。自分が自分らしく振舞えない相手なら友達とは言えねえだろ?それとも平気なのかよ?そんな偽りの関係でも・・・?」 「昔はね、自分ってこんなんじゃないのになんて思いながら演じてる部分があった。仲間はずれが嫌だったから」 「・・・・そう?・・・・なんだ・・・」 「1人って怖いし、吐きそうなくらい嫌だったもん」 「ワリイ!何か小難しい話になっちまった。ヘカテにしろここの迦具土の神さんにしろ不遇な連中ってところから、俺らに似てんのかなって思ってさ」 「神様と同列はだめでしょ。罰当たりな・・・それにそんなに不幸じゃないと思うよ。今の私達は」 「まあな。少なくとも今はな。自分で選んだそれぞれの道を歩いてるわけだから」 湧泉音はさっきからずっと黙り込んでいる。 |
| 月の女神 |
| それにしても、毎日必ず一度は鍵を探す。 いつものことだけどポケットの中、鞄の中、とありとあらゆる所を探して時間が空しく過ぎていく。 「ま~た、始まった!シッカの鍵探し」 「ウルサイ!黙ってて。ああもうどこやっちゃったんだろ」 「・・・・ないの・・・?」 「事務所に置いてきたんじゃねえのか?」 「ウルサイ!ウルサイ!」 大切なキーホルダーがついたヴェスパの鍵が無い。 階段を駆け下りるときに落としたんだろうか?それとも琥珀の言う様に事務所だろうか? 「ひょっとして、お前さっき手を洗った時にさ・・・」 「ああ!そうかも。ハンカチをポケットから出して・・・」 「・・・・あったよ・・・・」 手水舎の方からふいに湧泉音の姿が現れた。琥珀と言い争っている間に探してくれていたのだ。 「ゆね!!どこにあったの?」 「・・・・手・・・・洗う・・・・・」 「ああやっぱり、ありがとう?ゆね?」 湧泉音はじっと私のキーホルダーを見ている。 「・・・・ヘカテ・・・・月の・・・女神・・・」 「ヘカテは冥府の番人だってシッカが言ったろ?月の女神つったら梟を従えたアルテミス。俺だって知ってるぜ?」 「・・・・セレナもいる・・・・同じ神・・・・」 「なんだよ同じって、ヘカテ、アルテミス、セレ・・・ナ?不敵に微笑む月の女神が3人もいるのかよ?じゃあ梟も3匹か?」 琥珀が笑いかけた時、ホウホウと杜の中で梟が鳴いた。 「な、何だ!今の不気味な鳴き声は!!」 「・・・フクロウ?・・・・」 「梟だって?」 「何ビビッてんの?杜の賢者が挨拶してくれたんじゃない」 「い、いや、でも梟って・・・今、梟の話したばかりじゃないか。聞いてたのかよ、おれたちの話」 「こんな田舎だけど珍しいよ梟の鳴き声なんて。私だって滅多に聞かないのに、わざわざ会いに来てくれたのかもね?」 「・・・・知恵の・・・・神・・・・」 「幸福の使いとも言われてるし、ラッキーじゃない?」 「いや、ラッキーとか以前にシンクロ・・・・・」 「シンクロ??」 「いや、何でもない。神様っている・・・よな」 どの神様かは知らないけどな。 琥珀は湧泉音の持っている私のキーホルダーを手に取って独り言のように呟く。 顔を横に向けたヘカテのキーホルダー。 昔、家族兼用のクローゼットを整理していて、偶然見つけたものだった。直しこんでいる位ならお守りに持っておきたくて、どうしてもとママにせがんでやっと許してもらったのだ。 火事で亡くなった幼馴染の遺品なのだと、随分あとから教えられたのだけれど・・・・・・ |