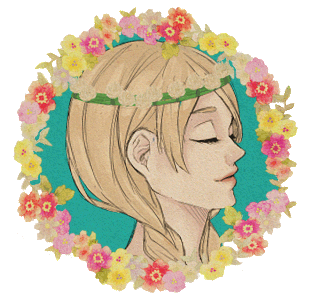| 天に咲く花 |
| けたたましいサイレンの響きと集まった野次馬の中で茅乃は必死に友の名を呼び続ける。 しかしそれは消防士の怒号と放水の音にかき消され、紅蓮の炎に呑み込まれていく。 時折上がる火柱からパチパチと火の粉があがり、赤い哀しみの花にも似たそれは暗闇を一層明るく照らしていた。 いつものように茅乃へと始まる手紙を読み終えて、激しく動揺する自分を止めることが出来ず帰郷の便を早めてはみたが、その間も湧き上がる不安を拭うことが出来なかった。 一刻も早く友に会い無事な顔を見るまでは、このどうしようもない不安が消えることはない。 生憎と最終便にしかキャンセルがなく、別府の街に着いた頃にはもうすでに日も落ちていた。 あと少し、もう少しで友に会える。 茅乃は自分の生家から僅かに離れた、神社の裏手にある翔子の家を目指した。 しかし子供の頃2人でよく遊んだ境内は、夜の静けさに包まれたいつもの様相とは逆に殺気立っていた。 3月と言うのに真冬のような寒さだった。 一晩あけた神社の境内はいつもの様に穏やかで、何事もなかったかのように見える。 子供の頃学校の帰り道に翔子と2人、拝殿の石段に鞄を置いたまま毎日遊んだ。 何がそんなに楽しかったのかは思い出せないが、難しい家庭環境にいる翔子もその時だけはよく笑った。 こんなにも足繁く通うのだから、何があってもきっとここの神様が守ってくれるだろうと、そんなたわいもない話をしては笑い転げていた。 茅乃はともかくあの時すでに翔子は、世の中が理不尽で不公平であることを知っていた。 何のために生まれて来たのだろうと、膝を抱えて泣いたこともある。 そんな彼女を無駄に励ましていただけではなかったのか? と強くあの男との結婚に反対するべきではなかったのか? 神様・・・何故?翔子は死ななければならなかったのですか? こんなにも世界は美しいのに・・・・・・ 冷たく澄んだ空気の中、空からの白い使者が舞い降りる。 無残な焼跡を覆い尽くすかのように降る雪は、ただ静かに沈黙し何も語ることはない。 夕方からやがて雨に変わるだろうと、天気予報は告げていた。 雪は天から降る花、そう何かの本で読んだことがある。 天上に咲く花。 翔子と2人の幼子をやすらかに包む花。 その一片がこぼれ落ちて、今、地上にいる茅乃のもとに届いていると信じたい。 突き上げる哀しみとこみ上げる痛みを、ただ身じろぎもせず受け止める以外なす術もなく、慟哭というのはこのことを言うのだと思った。 あの火事の後、自分の中に新しい命が宿っていることを知り、喜びよりむしろ今のこの耐えがたい苦しみが、胎内にどれほどの影響を与えるのか、目に見えぬ暗い影に怯えた。 「ごめんね」 茅乃は呟いたが、それはお腹の中の子供に対してなのか、翔子に対してなのかは、解らなかった。 神様・・・どうかお願いします。薄れ行く意識の中で、それでも彼女は祈り続けた。 羽・・・?炎と共に舞う白い羽根・・・・いや翼・・・ それが彼女の瞳に映った最後のものだった。 「まただ」 しばらく見なかったのに、疲れているせいかこのところ立て続けに火事の夢を見る。 あの女性はどうなったのだろう?傍らに倒れていた2人の子供は助かったのだろうか? 赤い炎に閉ざされた夢は、白く暖かな何かにふわりと包まれてそこで必ず目が覚めるのだ。 湧泉音も琥珀も起きる気配がない。 シッカはそっと起き上がり階下の倉庫に降りた。 片隅に置かれたイーゼルの布を恐る恐るはずすと、宙を舞う埃を気にもせず描きかけのその絵をじっと見つめた。 そのうち夢の中で包まれる白い何かはこれではないか?と思えて 中学の時から描いては消しの繰り返しで、未だ完成しないこの絵をそもそも何故?描きだしたのか思い出そうとした。 思えばあの頃から火事の夢を見始めたのだ。 そして見始めたきっかけは・・・・・? シッカは同じように埃を被った小さな箱を探し出すと、覚悟を決めて中にある手紙を取り出した。 紅鶴 茅乃 様 あの時、母に宛てた手紙の中からキーホルダーを見つけ出し、その図柄に強く惹かれたのである。 <ヘカテ>安産の神、旅人の守り神、そして他者によって殺められた者の魂を天国へと運ぶ、清めと贖罪の神。 母の字だろう。走り書きのメモにあの時は気が付かなかった。 母はシッカに手渡す時、安産の神様だからまだ貴女には早いわよ。そう寂しく笑って言っただけではないか。 殺められた者とは?この手紙の差出人と何らかの関係があるのだろうか? 一瞬の罪悪感の後、シッカは封筒から便箋を引き出して広げた。しかし、そこにある華奢な文字よりも、先に手からこぼれ落ちた新聞の切り抜きに目が行ったのだ。 放火殺人・・・・・ 黒字の大きな見出し、そして残酷な真実。 |