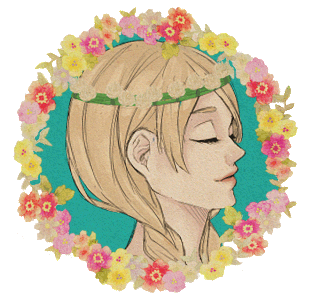| 羽 |
| 誰も知らない翔子と琥貴だけの指切り。 大丈夫だと翔子は思った。 どんなに暴力を振るわれても夫と別れなかったのは、1人で子供を抱えて生きて行く自信がなったからだ。 自分の足で立って生きる、と言うことをしたことがなかったのだ。 翔子を虐げた後の夫は優しい。 その優しさが3日と続きはしないことも解っている。 解っていても尚、1人で生きる孤独や不安よりはましだ、と自分をごまかし続けていた。 しかし、それが琥貴や生まれたばかりの泉にまで及びそうになった時、初めて彼女は夫に逆らった。 逆らった挙句殴られて気を失い、束の間の優しさに慰めを見出し、そしてまた殴られる日々の繰り返しの中で、何度死の誘惑に駆られたことだろう。 いつにもまして激しい暴力を受け、気を失っている間、翔子は不思議な夢を見た。 けたたましく泉の泣き声がする。 同時に夫の苛ついた怒声も響いた。 泉が危ない。 そう思っても体は動かずただ泣き声だけが耳に入る。 夫が泉に手を挙げた瞬間、琥貴が割って入りそのまま殴られて倒れるのが感じられた。 「琥貴!!やめて!!」 声にならない声で翔子は叫ぶ。 とその時、2人を包む白く大きな何かが彼女の目に飛び込んできたのだった。 「羽?・・・・天使・・・?」 目が覚めると夫の姿はなく、子供たちも眠りについていた。 慌てて抱き寄せると眠そうな目をこすりながら翔子に甘えてくる。 生きてる。 神様・・・ありがとうございます。 この時ほど命の重みを感じたことはなかった。私はこの子達を守らなければならない。 そう私は母親なのだから。 以来、翔子は夫の手から逃れる方法を探し続けた。 逃げようと思っていることを悟られてはならない。 終わることのない暴力は、彼女から生きる気力を奪い取っていく。 しかし、何度目かの死の誘惑に駆られてぼんやりと陸橋から下を覗いていた時、再びそれは訪れたのだった。 ここから身を投げたら死ねるかしら。 傍らでは琥貴が不安げに見上げている。 「こうちゃん。お母さんと別の世界に行く?」 「べつのせかいってどこ?」 「ここからううんと遠い所かな」 「とおいってどれくらいとおいの?あしたはかえってこれるの?」 「いいえ。帰ってはこれないわ」 「・・・・・やだ。あしたはれなちゃんのたんじょうびだもん」 「そっか。玲奈ちゃんのお誕生会だったわね」 「あっ!おかあさんきれいなはね。れなちゃんにあげたい」 「羽?」 ふと翔子の頬に触れる何かがあった。目を上げると白いそれが風と共に舞っている。 手を伸ばして掴めそうになった瞬間、するりと空に軌跡を描きながら還っていく。 それは決して手に入れる事の出来ない未来のようにも思えた。 「あの時の羽?いえ、そんなばかな」 もう一度目を凝らして見ても、空にはもう何も舞ってはいない。 「おかあさん。みてみてあそこ!きれい」 琥貴の小さな指が示す方を見ると、雲間から幾筋もの光の束が地上へと伸びている。 「まあ本当に綺麗ね」 「おかあさん。あれはなに?」 「さあ何かしら?お母さんにも解らないけど、天国のカーテンみたいね。」 「てんごくのかあてん?」 「きっと天使さんたちが隠れんぼしてるのよ」 「てんしさんのかくれんぼ?いいなあ」 「こうちゃんも天使さんと隠れんぼしたい?」 「うん。したい!」 そう?でももう少しあとにしようか。天使さんもきっと待っててくれるから」 「てんしさん、あそびにきてくれるかな」 「ええ。きっとまた会えるわ」 その後も白い羽は翔子に寄り添うように現れては消えた。 幻を見ているのかもしれない。 そう思いながらも、心のどこかで羽が自分を見守ってくれていると信じたかったのだ。 逃げる様に別府に帰り生活が少し落ち着いた頃、翔子はやっと手紙を書く気持ちになれた。 実家にも居場所はないと知りつつ、自立するまでの期間は親子3人で肩を寄せ合い、孫がもう使わなくなったからと近所の人から貰った2段ベッドが世界のすべてだった。 それでも琥貴は天井に空の写真を貼りめぐらせ、高い所で眠ることに喜びを隠せずにいた。 時折、下の段で眠る翔子と泉をじっと見下ろし、安心してまた自分の布団に潜り込む、いつしかそれが琥貴の日課のようになった頃、彼が興奮したように上の段から降りて来て叫んだ。 「おかあさん。てんしさんがきたよ」 「こうちゃん?天使さんがどこに来たの?」 「ここだよ。ぼくのすぐそばまで、てんしさんがきたよ」 「どうして天使さんって解ったの?」 「まっしろなはね。いつかおかあさんとみたはねだよ」 「羽が・・・見えたの?」 「うん。はねをつけたひとがそばにいたんだよ」 「羽を着けた人?」 「てんじょうのおそらをとんできてくれたんだよ」 「そう・・・天井のお空をね 」 翔子は琥貴が天井に貼った空の写真を見ながらふと思った。 もしかしたら、これのお蔭だったのかも・・・・ 取り出したキーホルダーに幼馴染の顔が重なる。 琥貴が出来た時、安産のお守りとして茅乃がくれたものだ。女神の横顔のそれはヘカテと言う名だった。 私はもう十分守られました。神様、今度は私の大切な友人をどうかお守りください。 そう祈ると茅乃宛ての手紙にそっと入れ込んで窓の外を見た。 いつか見た空だ・・・・・・ 幾重にも重なった光の梯子が伸びて、雲間からの木漏れ日が部屋の中を明るく照らす。眩しさに思わず翔子は目を細めた。 |